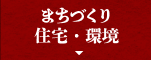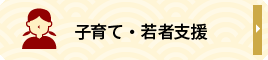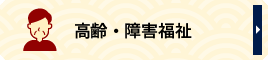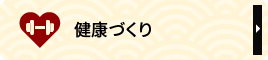絹本著色骸骨図
ページID:644397700
更新日:2024年2月20日
誓教寺
平成8年登載
満月に照らされ、浮かび上がる岩と笹竹をバックに、灯籠を提げて立つ骸骨の姿が描かれています。月の外縁、画面右端部、画面最下部及び骸骨の骨格まわりに薄く墨隈をほどこし、影を表現しています。
表現は全体的に墨画風ですが、骸骨をはじめとする諸景物の細部における執拗なまでの描写、割筆を用いた土坡、点苔や笹の葉脈を示す藍、竹の節の白、灯籠の房と周縁部に見られる朱の鮮やかな色彩の使用などから、幻想的な中にも生々しさを感じさせます。
また、骸骨の周囲の影は髪の長い女性の立ち姿を見立ててあり、灯籠の吊り具は絵師の画号の卍型に描くなどの意匠も特徴的です。
本図の作者は、江戸時代後期の著名な浮世絵師、葛飾北斎(1760~1849)。画面右下の落款により、己酉、嘉永2年(1849)の正月、北斎90歳の時の作品とわかります。北斎が浅草聖天町遍照院(現・浅草6丁目)境内の長屋で没したのは、数えで90歳、嘉永2年4月18日のことです。画中の己酉正月九十老人卍筆の款記は、本図が北斎最晩年の作の一つであることを示しています。大きさは、縦125センチメートル、横77センチメートル。
北斎の描く骸骨といえば、錦絵の連作『百物語』中の『小はだ小平二』がよく知られていますが、本図のような本格的な骸骨図はほかには例がありません。北斎は、文化3年(1806)頃、接骨家名倉弥次兵衛に入門し、人体の骨格の勉強をしたといわれ、本図を描くに当たっては、このときの経験を参考にしたことは容易に想像できます。
しかし、人体の骨格の細部までが世に知られるようになったのは、安永3年(1774)における日本初の本格的西洋医学書の翻訳書・解体新書の刊行、またそれに続く蘭学者たちの業績によるものが非常に大なるものでした。同時代に生きた北斎も蘭書を見ている可能性が大きいと思われます。
大槻玄沢が杉田玄白より増補改訂を命ぜられて文政9年(1826)に刊行した『重訂解体新書』の付図『銅版全図』中の「全骸前図」には、肋軟骨(肋骨の内側の短い骨)が描かれていますが、本図にはこれが欠けています。天保7年(1836)上演の歌舞伎を描いた歌川国芳の錦絵『相馬の古内裏』や、増補改訂以前の小田野直武の手になる『解体新書付図』には肋骨と肋軟骨の区別がされていることなどから、北斎は直接蘭学者の手ほどきは受けておらず、『銅版全図』に代表されるような、書物を手本として描いたものと考えられます。
本図は、『恠談牡丹灯籠』の元となった明の瞿祐作『剪燈新話』に依拠していると思われます。『恠談牡丹灯籠』は、三遊亭円朝作の有名な怪談で、明治17年に『恠談牡丹灯籠』として速記本が刊行されました。その執筆は、円朝自身の回顧によると、文久元年(1863)であり、本図制作時より14年後のことです。
北斎が題材にしたと思われる中国の怪談集・剪燈新話は、日本では浅井了意によって翻案され、寛文6年(1666)『伽婢子』として、内容も日本向きに直して刊行され流布しました。明治時代以後に牡丹灯籠を題材にした絵画の大部分は、円朝が作り出したお露とお米の二人を同時に描きますが、これに対し本図は、亡霊となった一人のみを描いています。また、『剪燈新話』『伽婢子』ともに、灯籠に牡丹の花を配していますが、本図では牡丹の花は描かれていません。
以上のように、本図は、物語を絵画化するにあたっての、北斎独自の感性がよく表現されている作品で、その画題に選んだ『牡丹灯籠』は、その画歴を考える上で非常に重要です。
誓教寺では、現在でも墓参する方が後を絶たず、毎年命日の4月18日は「北斎忌」として彼の偉業を偲び法話会が開かれています。

全体図

落款・印章
お問い合わせ
生涯学習課文化財担当(生涯学習センター)
電話:03-5246-5828
ファクス:03-5246-5814