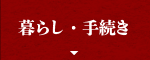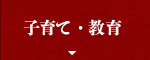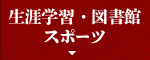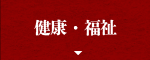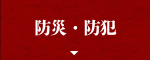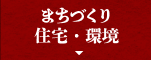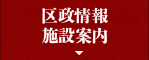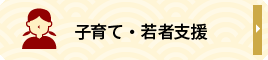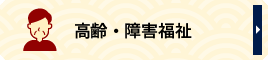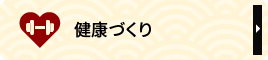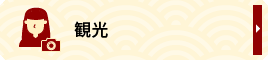女性の飲酒はほどほどに
ページID:559348504
更新日:2025年7月7日
●飲酒習慣
飲酒習慣がある人の割合は、女性では国より高くなっています。
| 男 | 女 | |
| 台東区 | 33.8% | 23.2% |
国 |
37.4% | 15.6% |
国保データベース「特定健康診査」生活習慣に関する質問項目 の状況(40 歳~64 歳)より抜粋 令和5年度累計
●飲酒量
台東区では、男女ともに国よりも高くなっています。
特に女性の「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合」は、国の2倍程度となっています。
| 男 | 女 | |
| 台東区 | 11.7% | 4.7% |
| 国 | 8.4% | 2.2% |
国保データベース「特定健康診査」生活習慣に関する質問項目の状況(40歳~64歳)より抜粋 令和5年度累計
生活習慣病のリスクを高める量とは?
厚生労働省から令和6年に公表された「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」によると
1日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上 と定義しています。
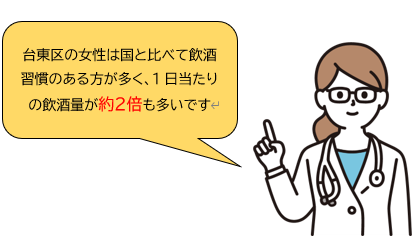
女性は男性よりお酒に弱い体質です。
女性は、一般的に、男性と比較して体内の水分量が少なく、分解できるアルコ ール量も男性に比べて少ないことや、エストロゲン(女性ホルモンの一種)等の はたらきにより、アルコールの影響を受けやすいことが知られています。
アルコールを分解する体内の分解酵素のはたらきの強い・弱いなどが、個人によって大きく異なります。
アルコールのリスクを理解した上で、次に示す純アルコール量に着目しながら、自分に合った飲酒量を決めて、健康に配慮した飲酒を心がけることが大切です。
純アルコール量(g)は摂取量(ml)×度数または%/100×0.8(比重)で計算できます。
単にお酒の量(ml)だけでなく、お酒に含まれる純アルコール量(g)について着目することは重要です。
女性の飲酒によるリスク
●乳がんと飲酒の関係
女性の中で最も多いがんである乳がんも、飲酒と関係があると言われています。乳がんのリスクとして、女性ホルモンや運動不足、肥満など様々な要因が知られています。アルコールもその一つで、飲酒量に比例してがんのリスクも高まります。
●妊娠中や授乳中はお酒を控えましょう
妊娠中は少量であったとしてもお酒を飲んではいけません。妊娠中の女性が飲酒をすると、胎盤を通じてアルコールが胎児の血液に入り、生まれてくる赤ちゃんに体重の減少・脳の障害など、様々な悪影響が出てくる原因となる可能性があります。
また、授乳中のお母さんの飲酒は、母乳を通じて赤ちゃんにお酒飲ませることになってしまいます。アルコールが母乳に移行する割合は高く、血液中のアルコール濃度と母乳中の濃度はほぼ同じと言われています。授乳中にお酒を飲むのは控えましょう。
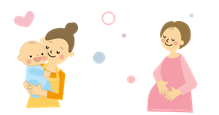
飲み過ぎを防ぐには
(1)自らの飲酒状況等を把握する
(2)あらかじめ量を決めて飲酒をする
(3)飲酒前又は飲酒中に食事をとる
(4)飲酒の合間に水(又は炭酸水)を飲むなど、アルコールをゆっくり分解・吸収できるようにする
(5)一週間のうち、飲酒をしない日を設ける(毎日飲み続けるといった継続しての飲酒を避ける)
健康に配慮した飲酒をこころがけましょう

お問い合わせ
浅草保健相談センター
電話:03-3844-8172
ファクス:03-3844-8178
台東保健所 保健サービス課
電話:03-3847-9497
ファクス:03-3847-9467