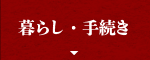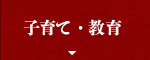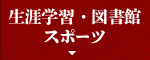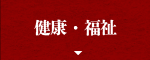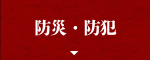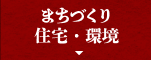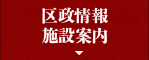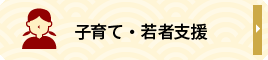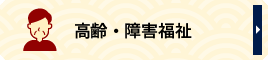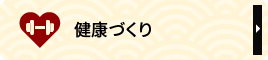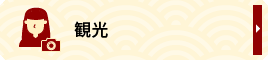令和7年第1回区議会定例会区長所信表明
ページID:218708402
更新日:2025年2月5日
はじめに
令和7年第1回区議会定例会の開会にあたり、私の区政運営に対する所信を申し述べ、区議会及び区民の皆様のご理解、ご協力を賜りたいと存じます。
新年を迎え、本区が中心舞台となる、大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の放送が始まりました。吉原神社の近くに観光拠点施設「江戸新吉原耕書堂」が開設されたほか、今月1日には、浅草に「大河ドラマ館」がオープンするなど、関連事業が続々と開始されております。
私は、本区の地域資源である「江戸たいとう」に注目が集まる、この機会を十分に活用し、区民の皆様と、本区の力の源である豊かな文化資源の魅力を再認識するとともに、区内外へ発信することで、多くの人々を惹きつける活力あるまちの実現に繋げてまいります。
さて、国は、経済対策の基本的な考え方について、当面の対応として物価高に伴う負担軽減を図るとしつつ、中長期的な成長力の強化に向けた取組を強化し、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を目指すとしています。
区においても、物価の高騰や労働力不足などが、依然として区民生活や事業活動に影響を及ぼしていると認識をしております。また、同時に、社会経済状況などの変化を的確に捉え、必要な施策を中長期的な視点に立って、着実に推し進めていく必要があると考えています。
そこで、継続する物価高騰への対応として、新たな低所得者世帯向けの給付金や、介護・障害福祉サービス等事業者に対する光熱費等の支給を進めています。
また、未来を見据え、これまで力強く進めてきた子育て世帯への支援や、福祉人材の確保等にかかる事業者への支援を充実するとともに、区内中小企業に対する相談機能の強化や人材確保への支援を新たに実施するなど、取り組みを推進してまいります。
私は、本区が将来にわたり、魅力にあふれ活力に満ちた都市であり続けられるよう、全力で区政運営に邁進してまいります。
誰一人取り残さない、支援の仕組みづくりについて
それでは、まず、誰一人取り残さない、支援の仕組みづくりについて申し上げます。
少子高齢化や核家族化の一層の進行、住民相互のつながりの希薄化等により、8050問題やヤングケアラー等、複雑かつ複合的な問題を抱える方が増え、既存の相談体制や公的サービスのみでは問題の解決が難しい状況となっています。
そこで、各相談窓口において、問題の背景にある、家庭の状況や生活課題も含めて受け止め、支援に繋げるため、新たな研修等を実施し、職員の対応力向上を図ってまいります。
また、新たに地域福祉コーディネーターを配置し、組織横断的な対応に向けた総合調整を実施することで、相談から適切な支援に繋げる仕組みづくりを推進します。
さらに、区のみでは対応が困難な事例については、ケースごとに、関係機関を交えた会議等を開催し、アウトリーチを含む適切な支援方針を決定するほか、社会とのつながりや生きがいづくりに繋げていくなど、誰一人取り残さない支援の仕組みづくりに向け、取り組みを推進してまいります。
災害対応力の強化について
次に、災害対応力の強化について申し上げます。
区では、地域防災計画を修正し、減災目標を達成するための重点事項に、行政の備蓄のあり方や家庭内備蓄の促進などを位置づけるとともに、能登半島地震での教訓を踏まえ、区の備蓄品の大幅な拡充を図りました。
今後は、現在作成している「台東区災害時備蓄物資整備指針」の考え方に基づき、避難所や防災拠点倉庫における備蓄品の更なる適正配置を進めるとともに、備蓄の分散化のため、連携都市である茨城県筑西市に備蓄倉庫を設置します。
また、災害時におけるトイレ対策は「命を支える社会インフラ」のひとつであり、迅速かつ安定的に実施することが重要です。
そこで、発災後の状況に応じた利用可能なトイレの選定や、その使用方法を具体的にまとめた、「(仮称)台東区災害時トイレ確保・管理指針」を策定し、災害時の衛生環境の保全と災害対応力の強化に努めてまいります。
都区財政調整について
次に、都区財政調整について申し上げます。
今年度の都区財政調整協議は、都区間の配分割合を見直すという、非常に重要な協議となりました。
令和5年度の協議では、都区の考え方に大きな隔たりがありましたが、一昨日、開催された都区協議会において、特別区の配分割合を55.1%から56%に変更し、併せて、災害対応経費等に充当される特別交付金の割合を5%から6%とすることで、合意を得ることができました。
これは、首都直下地震等に対し、備えを充実させていくとともに、児童相談所の運営に関する都区の連携・協力を、引き続き円滑に進めていくことを踏まえたものであり、都区が、東京の未来を共に創り上げるための合意としています。
今後とも、双方の真摯な協議により、都区財政調整制度の安定的な運営に尽力するとともに、都区が抱える課題の解決に向けて、これまで以上に連携を密にし、取り組んでまいります。
令和7年度予算案について
次に、令和7年度予算案について申し上げます。
区の財政状況について、歳入は、特別区税や特別区交付金の増を見込んでいますが、所得控除の見直し等による影響には十分注意する必要があります。また、歳出では、子育て支援、高齢者・障害者へのサービスの充実のほか、老朽化した区有施設の更新に多額の費用がかかることが見込まれます。
こうした状況であっても、財政の硬直化や将来負担に注意しながら、社会経済状況の動向を踏まえた行政課題に積極的に取り組む必要があります。私は、区民に最も身近な基礎的自治体の長として、本区の輝かしい未来に向け、福祉や子育てニーズの変化に的確に対応していけるよう予算を編成しました。
それでは、予算案の主な事業について、長期総合計画の基本目標ごとに申し上げます。
あらゆる世代が生涯にわたって成長し輝くまちの実現について
まず、あらゆる世代が生涯にわたって成長し輝くまちの実現について申し上げます。
次代を担う子供・若者がのびのびと育ち、自らの希望に応じてその意欲と能力を活かすことができる環境を整えることは、地域の活力向上と本区の持続的発展にとって、大変重要です。
今年度改定する「台東区次世代育成支援計画」では、子供・若者を多様な人格を持った個として尊重し、その権利を保障していくことを基本目標の1つに位置付け、子供・若者、子育てにやさしい社会づくりのための取り組みを進めてまいります。
児童虐待は、子供の心身の成長や人格の形成に影響を与え、次の世代にもその影響が及ぶおそれのある、重大な権利の侵害です。子供の生命を脅かす悲惨な事態を未然に防ぐためには、虐待を早期に発見し、適切な支援に繋げていくことや、子育てに係る心身の負担を軽減するための取り組みを進めることが大切です。
そこで、相談員に対し、タブレット端末を1人1台配備し、訪問先における迅速な情報共有を可能にすることで、より早期の対応に繋げていきます。また、保護者の負担軽減に向けて、夜間帯においても、養育支援ヘルパーによる家事の援助や訪問による助言指導を実施できるよう、事業の充実を図るとともに、地域の里親等を活用した協力家庭制度を新設し、一時的に子供を預かるショートステイの受け入れ先を拡大します。
また、すべての児童・生徒が、適切な教育環境の中で、健やかに自分らしく成長できるよう支援体制を構築することが重要です。
そこで、石浜小学校における自閉症・情緒障害特別支援学級の設置に向け、環境整備や相談の受付を開始し、より一層きめ細かな指導が受けられるよう取り組みを進めてまいります。
また、不登校児童・生徒の増加に対し、個々の状況に合わせた支援の充実を図るため、すべての区立小・中学校に、別室で学習のサポートや相談等を実施する支援員を配置するとともに、上野中学校に東京型不登校特例校であるチャレンジクラスを開設することで、登校や社会的自立に向けた支援を実施し、学びや居場所の選択肢を増やしてまいります。
さらに、子育てに関する不安を軽減し、子育て世帯が地域のサポートを受けながら、いきいきと安心して子育てができるよう、一層支援を充実していく必要があります。
そこで、産前産後支援ヘルパーの利用可能期間を拡大するとともに、保護者の働き方の多様化によるニーズの変化に対応するため、区立幼稚園の全園で預かり保育を実施します。
また、近年、小中学校での教育活動に要する費用が増加傾向にあります。
そこで、保護者の経済的な負担を軽減し、教育環境の充実と子育て支援の更なる拡充を図るため、区立小中学校と特別支援学校に通う児童・生徒が教育活動で使用する補助教材や学用品等の費用を助成してまいります。
いつまでも健やかに自分らしく暮らせるまちの実現について
次に、いつまでも健やかに自分らしく暮らせるまちの実現について申し上げます。
区では、今年度改定する「健康たいとう21推進計画」において、基本目標に健康寿命の延伸を追加しました。
区民が主体的に健康づくりに取り組むことで、生涯を通じて、心身ともに健康で質の高い生活を送ることができるよう、様々な事業に取り組んでまいります。
まず、区民が自らの健康状態に関心を持ち、手軽に健康づくりに取り組めるよう、日頃の生活習慣などを可視化できるスマートフォンアプリを導入します。アプリの活用により、区民が、ウォーキングイベントや講演会参加などの健康行動を始めるきっかけづくりと、その取り組みの継続を支援することで、健康意識の向上と生活習慣の改善、更には健康寿命の延伸に繋げてまいります。
また、地域における自主的な介護予防の取り組みを支援するため、健康遊具を活用した運動教室の実施場所を拡充します。
今年は、団塊の世代の方々が75歳以上となり、認知症高齢者の増加が見込まれます。
そこで、区民が、早期に認知機能の低下に気づくきっかけとなるよう、65歳以上の対象年齢の方にチェックリストを送付し、認知症の可能性が高い方の医療機関受診を促すことで、早期発見による治療等に繋げてまいります。
また、成年後見制度の利用支援において、新たな会議体を立ち上げ、司法等に精通した専門職の知見を活用し、本人の状況に応じた後見人等の選出を実施することで、制度の利用を必要とする方が、いつまでも自分らしい生活を継続できるよう支援してまいります。
区では、在宅療養支援窓口を、区立台東病院に設置し、在宅療養に関する相談対応や関係機関との連携を実施してきました。しかしながら、家族による介護や病状急変時の対応に不安があるという声も聞かれます。
そこで、在宅療養に関する相談窓口や医療・介護関係者の役割などを記載した「在宅療養ハンドブック」を作成し、療養生活の具体的イメージを持ってもらうことで、不安の軽減と理解の促進を図り、適切な支援に繋げてまいります。
また、40歳未満の若年がん患者は、介護保険が適用されないため、療養に伴う経済的な負担が大きくなることがあります。
そこで、ケアプランの作成や介護サービス、福祉用具の利用に係る費用を助成し、不安の軽減を図るとともに、安心して在宅での療養ができるよう支援してまいります。
活力にあふれ多彩な魅力が輝くまちの実現について
次に、活力にあふれ多彩な魅力が輝くまちの実現について申し上げます。
今年は、寛永寺が創建400周年を迎えることから、「上野の山文化ゾーンフェスティバル」において記念イベントを開催します。今後とも、関係機関と連携し、文化の集積地である上野の山の魅力を、広く発信してまいります。
また、訪日外国人旅行者数が、本格的に回復する中、区民生活の質の確保と観光客の満足度向上の両立を一層推進していくため、新たな観光振興方針の策定に向けた実態調査等を進めてまいります。
さらに、訪日外国人観光客を対象として、区内事業者の商品マーケティング調査を浅草文化観光センターで行い、その結果を、インバウンド市場や海外市場への展開に意欲のある事業者に活用してもらうことで、区内事業者の更なる発展を支援してまいります。
そして、大河ドラマ「べらぼう」の放送により、全国から注目が集まる、この機会を捉え、区内事業者の、江戸の魅力溢れる商品の販売の場を、区内外で展開いたします。
また、若い世代に影響力をもつ女性ファッション誌編集部と連携し、浅草北部地域周辺のPRを行うことで、SNS等を活用した更なる発信に繋げ、地域にある飲食店や商店街などの賑わいの創出を図るなど、事業者と区が一丸となって、区内産業の振興を一層推進してまいります。
誰もが誇りや憧れを抱く安全安心で快適なまちの実現について
次に、誰もが誇りや憧れを抱く安全安心で快適なまちの実現について申し上げます。
人を中心とした魅力あるまちづくりを進める上では、都市に存在する人流や交通量などの様々なデータを蓄積、活用して、まちづくりを検討することが重要です。
本区では、公民連携によるまちづくりの取り組みを推進していくため、区全域の3D都市モデルの整備をいち早く開始し、多様な主体がまちの将来像をシミュレーションできる環境づくりを進めてきました。今後は、人流等の多様なデータを重ね合わせることで、災害発生時の避難シミュレーションに活用するなど、防災や観光等の分野にも展開してまいります。
また、本区には多くの観光客が訪れ、災害時には、多数の帰宅困難者の発生が見込まれます。
そこで、これまでの取り組みに加え、浅草地域を対象とした避難誘導指針の策定に向け、地域と一体となった検討を、開始します。同時に、訓練等を通じた、検証・改善を図ることで、おもてなしのひとつである、まちの安全安心への対策をさらに推進してまいります。
また、環境負荷の軽減や日常における健康増進に効果的な自転車は、多様な移動手段の一つです。
区では、これまで、シェアサイクルの普及に向けた実証実験を行うなど、身近な移動手段である自転車の利便性向上を図ってまいりました。今後、更なる活用を推進するため、通行・駐輪環境の整備及びルールやマナーの啓発を含めた自転車活用施策を計画的に推進していく「(仮称)台東区自転車活用推進計画」を策定します。加えて、放置自転車の撤去と駐輪場運営を連携させた総合的対策を実施することで、誰もが安全・安心で快適に自転車を利用できる環境づくりを進めてまいります。
また、本区は、江戸の昔から日々の生活の中に「花とみどり」が根付き、地域の文化となっています。
そこで、「花の心プロジェクト」の更なる普及啓発を通じて、多くの区民や事業者の皆様が、身近な場所で花やみどりを育て、心豊かになる機会を提供していくとともに、共同住宅が多い本区の特性を踏まえて、新たに「ベランダ緑化助成」を開始し、身近な場所で自然に親しむことができる、みどり豊かなまちの形成を一層推し進めてまいります。
また、森林保全の意識醸成や姉妹都市との交流を深めるため、子供とその保護者が、宮城県大崎市主催の「おおさき未来の森づくり」に参加し、植樹や自然体験を行うツアーを実施します。
多様な主体と連携した区政運営の推進について
次に、多様な主体と連携した区政運営の推進について申し上げます。
近年、女性であることから直面する様々な困難が、複雑化・多様化・複合化し、個人の力だけでは問題を解決することが難しい状況のなか、区として支援を強化していく必要があります。
そこで、はばたき21相談室に、新たに女性相談支援員を配置するほか、経済的自立に向けた専門的な相談を開始するなど、機能の強化を図ります。また、個々の状況に応じた最適な支援を検討する支援調整会議を設置するとともに、女性支援の実績を有する民間団体等と連携するなど、継続的な支援を実施してまいります。
また、今後も、限られた人材で、多様化する区民ニーズに的確に対応していくためには 、本区のDXをこれまで以上に加速させる必要があります。
そこで、全庁横断的な連携を強化するため、「(仮称)DX推進会議」を新たに設置し、既存のデジタルツールや生成AIなどの新たな技術の利活用を一層促進してまいります。さらに、庁内のBPRやシステム活用の支援などに取り組む、「DX推進サポーター」を育成することで、庁内のDXを強く推し進めてまいります。
また、行政手続きに伴う待ち時間の短縮や申請書等の記入に係る負担をより一層軽減する必要があります。
そこで、スマート窓口システム導入に向け、各種業務の見直しに取り組むほか、ご遺族等の行政手続きに係る負担の軽減を図るため、「おくやみコーナー」を庁舎1階で実施します。
おわりに
最後に申し上げます。
来月、3月9日に、「下町風俗資料館」が展示内容を一新し、「したまちミュージアム」としてリニューアルオープンします。下町の街並みや暮らしを再現した原寸大展示等を通して、江戸から続く本区の魅力を再発見してもらう展示空間としました。是非、区民の皆様にもご来館いただければと思います。
また、4月から、区内の小・中学生を対象としたフェンシング教室を実施します。パリオリンピック金メダリストの松山選手による指導を予定しております。さらに、台東リバーサイドスポーツセンターにおいて、フェンシングの練習ができる環境の整備を進めてまいります。
そして、今年は、本区も大きな被害を受けた東京大空襲から80年を迎える節目の年です。来月開催する「平和のつどい」等を通じて、恒久平和に向けた意識の醸成を図り、次の世代に引き継いでいけるよう取り組んでまいります。
本年も、台東区の更なる飛躍に向け、区民の皆様、区議会の皆様の、お力添えをいただき、着実に区政を前進させてまいります。ご理解とご協力をお願い申し上げ、私の所信といたします。
なお、本定例会には、「令和7年度東京都台東区一般会計予算」ほか35件の議案を提出しています。よろしくご審議のうえ、いずれも可決賜りますようお願い申し上げます。
(注 本文は口述筆記ではないため、表現その他若干の相違があります。)
服部区長
お問い合わせ
企画課
電話:03-5246-1012
ファクス:03-5246-1019